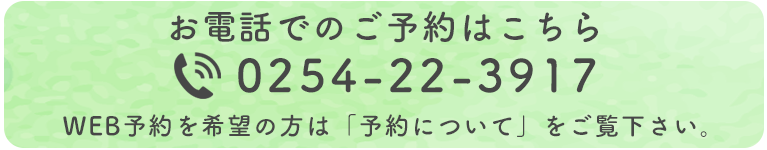症状別のお悩み
頭痛
頭痛は片頭痛、緊張型頭痛、群発頭痛などの「頭痛という病気」である一次性頭痛と、放っておくと怖い二次性頭痛に分かれます。
病歴聴取、神経学的検査、画像診断で二次性頭痛をしっかりチェックすることが重要です。
二次性頭痛の一例として
くも膜下出血、脳出血、脳腫瘍、髄膜炎、慢性硬膜下血腫 などがあります
二次性頭痛は緊急性が高く放置すると生命にかかわります。
- 今まで経験したことのないような激しい頭痛。
- 脱力、しびれ、ふらつき、言語障害などの神経症状を伴う頭痛。
- めまいや嘔吐を伴う激しい頭痛。
- 日を追うごとに強くなる頭痛。
- がんや免疫不全をお持ちの方の頭痛。 など
様子をみることなく早期の受診をしてください。
一次性頭痛
- 片頭痛
ズキンズキンとした拍動性の頭痛で、光や音に過敏になるのが特徴です。動くと頭痛が悪化し、仕事や日常生活への支障が大きく、寝込んでしまう方もいます。 - 緊張型頭痛
圧迫感、締めつけ感のある頭痛です。両側性で生活に支障の出るほど強くなく、日常動作で悪化しないのが特徴です。診察では頭蓋周囲筋(後頭部、首筋の筋肉、側頭部の筋肉など)の圧痛がみられることがあります。 - 群発頭痛(三叉神経・自立神経性頭痛)
激しい痛みが片方の目の奥から側頭部にかけて起こります。涙や鼻水が出たり、結膜充血、まぶたの浮腫、発汗などを伴います。発作頻度が高く、夜間に多い、連日起こるといった特徴があります。 - 後頭神経痛
ズキンとした電気が走るような短時間の痛みが何回も繰り返す頭痛です。肩こりや首のこりが原因になることが多く、大後頭神経、小後頭神経、大耳介神経などが刺激され神経痛を生じます。時には帯状疱疹が原因のこともあり、皮疹が出ていないか確認することが大切です。 - 薬物乱用頭痛
鎮痛薬を飲む回数が増えてしまい、それを継続的に服用している(1ヶ月に10日以上、薬により15日以上、3ヶ月以上にわたり使用)ことにより生じる頭痛です。
物忘れ
年齢を重ねると自然と物忘れが多くなってきます。
自分は認知症なのではないかと不安に思われる方も多いと思います。
加齢による物忘れと、認知症による物忘れはどこが違うのでしょうか?
加齢による物忘れ
体験の一部を忘れる
- 眼鏡をどこにしまったか忘れる
- 食事をしたことは覚えているが何を食べたか忘れる
- 人の名前や地名を忘れる など
物忘れを自覚している
日常生活に支障はない
時間場所などの見当がつく
認識力や判断力には問題がない
認知症による物忘れ
体験したすべてを忘れる
- 食事をしたこと自体を忘れる
- 新しいことが記憶できず約束や予約を忘れてしまう など
認識力や判断力に問題があり日常生活に問題が生ずる
物事を計画を立てて実行することができない
同じことを何度も言ったり聞いたりする
時間や場所がわからなくなる
道に迷う
認知症の種類
- アルツハイマー型認知症
- 脳血管障害性認知症
- レビー小体型認知症
- 前頭側頭型認知症
- 治療可能な認知症
正常圧水頭症、慢性硬膜下血腫、甲状腺機能低下症、ビタミン欠乏症、うつ状態などにより引き起こされる認知症もあります。これらは治療可能な認知症ですので、「もう歳だから」と放置せず、早めの受診をお勧めします。
めまい・ふらつき
脳の疾患に原因があるめまい
めまいを誘発する代表的な脳疾患として
- 脳出血
- 脳梗塞
- 脳腫瘍
などがあげられます。
小脳や脳幹になんらかの異常(血管障害や腫瘍による圧迫など)があると
ふらつく
ふわふわとした浮遊感がある
動いたり揺れたりする
といった症状がみられます。
また、
うまく喋れない
まっすぐ立っていられない
まっすぐ歩けない
麻痺の症状が出ている
など、これらの症状があらわれるケースは、きわめて危険な「めまい」である恐れがあります。
迷うことなく、速やかに専門医を受診してください。
循環器系・内科的に原因があるめまい
めまいを誘発する代表的な循環器系・内科的疾患として
- 高血圧症
- 低血圧症
- 低血糖症
- 貧血
- 不整脈
などがあげられます。
耳の疾患に原因があるめまい
代表的な疾患として
- 良性発作性頭位めまい症
- 前庭神経炎
- メニエール病
- 突発性難聴
などがあげられます。
手足のしびれ・痛み
脳に原因がある場合
- 脳血管障害
脳血管障害とは、脳出血、脳梗塞などによって脳神経経路に障害が生じた状態です。
脳の障害部位とは反対側の半身の手足にしびれや麻痺が起こります。
(例:左脳側に障害が生じると右手や右足に症状が現れる)
半身だけに突然のしびれや麻痺を感じた方は、注意が必要です。 - 脳腫瘍
脳血管障害と同様に、脳腫瘍も体の片側にしびれや麻痺が起こります。
ただ、脳血管障害のように突然の症状ではなく、脳腫瘍の肥大にあわせて感覚が徐々に鈍くなってきたり、ゆっくりと症状が進行するという特徴があります。
脊椎に原因がある場合
- 変形性頚椎症
加齢によって頸部の骨(首の骨)が変形して、骨に出っ張りができた状態を変形性頚椎症といいます。
この骨の出っ張りによって脊髄や腕や手に伸びる神経根が圧迫されて
腕や手のしびれや痛み
力が入らない
といった症状を引き起こすことがあります。 - 頸椎椎間板ヘルニアと腰椎椎間板ヘルニア
頭と骨盤の間にある骨を背骨(せぼね)といいますが、この骨の間には椎間板(ついかんばん)と呼ばれるクッションの役割をはたしている部分があります。
頸椎椎間板ヘルニアはこのなかの頸部(首付近)の椎間板が変形して飛び出すことで、神経根や脊髄を圧迫して症状を引き起こす疾患です。変形性頚椎症と同様に
腕や手のしびれや痛み
力が入らない
などの症状が起こります。
これが腰部の椎間板で起こるものを腰椎椎間板ヘルニアといいます。
股関節、ひざ関節、足関節と足指の部分に
しびれや痛み
力が入らない
などの症状が起こります。
末梢神経に原因がある場合
- 胸郭出口症候群
首と胸の間を通る神経が圧迫されて起こる疾患です。
手・首・肩・腕あたりに痛みやチクチクする感覚(錯感覚)が起こります。 - 手根管症候群
手首付近にある骨と靭帯で生成されたトンネル部分を手根管といいます。
手指の筋肉に通じる神経は、この手根管を通りますが、なんらかの障害によって神経が圧迫されてしまうと、手にしびれや痛みなどを感じます。
内科的疾患に原因がある場合
- 糖尿病性神経障害
糖尿病によって細い血管(毛細血管)がダメージを受けると手指や足先などにしびれや痛みを感じることがあります。
これは糖尿病による血行障害によって末梢神経がダメージを受けていることが原因です。 - ビタミン欠乏
ビタミンが不足することで神経障害が起こることがあります。
脚気(かっけ)は、ビタミンB1が欠乏して起きる疾患です。末梢神経に障害が現れ、足のしびれから感覚麻痺などを引き起こします。
意識障害・てんかん
意識障害とは
こんな症状はありませんか?
- 眠りがちになる
- 会話の途中で混乱することがある
- 集中力を欠いたり考えがまとまらないことがある
- 明瞭に思考できないことがある
このように意識障害とは「意識が清明ではない状態」のことを示します。
意識障害の程度は大きく分けて下記の4つに分類されます。
傾眠:外部からの刺激や情報に反応し覚醒するが放っておくと眠ってしまう
混迷:体を揺する大声で呼びかけるなどの強い刺激を与えると反応する
半昏睡:強い刺激に反応して刺激を避けようとしたり顔をしかめたりする
昏睡:外部からの刺激に全く反応せず眼は閉じたままの状態
意識障害の症状が現れる主な疾患
- 脳梗塞、脳出血
- 低血糖
- 糖尿病
- 低酸素症
- 尿毒症
- 急性アルコール中毒
- 低体温症
- 熱中症
- 不整脈
- 急性心不全 など
てんかん
てんかんとは、意識障害やけいれんなどを発作的に起こす慢性的な脳の疾患です。
意識をなくしてしまい手足をつっぱらせた後にガクガクと全身けいれん発作が起こる症状がみられますが、意識がある発作やけいれんのない発作もあります。
診断には患者様ご本人だけでなく、実際に発作を目撃された方からの情報がたいへん有用です。
首・背中・腰の痛み
末梢神経障害
末梢神経とは脳や脊髄などの中枢神経から分かれて、全身の器官や組織に分布する神経のことです。
末梢神経は大きく以下の3つに分けられます。
運動神経:全身の筋肉を動かす機能
感覚神経:痛み、冷感、触れた感触など皮膚の感覚や振動、関節の位置などを感じる機能
自律神経:血圧や体温の調節、心臓や腸など内臓の働きを調節する機能
末梢神経障害とはこれらの神経が何らかの理由でダメージを受け働きが悪くなることで引き起こされる様々な障害のことです。
主な症状はそれぞれ以下になります。
運動神経の障害→手脚の筋力が低下し筋肉が瘦せてきた
感覚神経の障害→しびれや痛みが生じたり逆に感覚が鈍くなったり消失したりする
自律神経の障害→手足の発汗障害や異常知覚などがみられる
これらの障害は単独で生じることは少なく、ほとんどが複合されて症状が現れます。
筋肉の痛み
過度の運動やウイルス感染に伴う筋肉痛はだれもが経験する一般的な症状です。しかし、緊急の対応を必要とする筋肉痛の原因として横紋筋融解症があります。急激に筋肉細胞が壊れ、腎不全に至ることもあります。薬剤(スタチン系やフィブラート系などのコレステロール値を下げる薬やコデインなどの咳止め薬など)、カリウム欠乏、熱中症、脱水、外傷などで発症します。運動に関連して起こる筋肉痛の中にも病的なものがあります。グリコーゲンの代謝異常症(糖原病)では運動開始直後に筋肉痛が起こり運動を続けているうちに痛みが軽減することが特徴です。一方、長距離走など筋肉の持久運動で痛みがでてくる場合は脂肪酸代謝異常症が疑われ、横紋筋融解症を起こすことがあります。
いわゆる"こむら返り"といわれる有痛性筋痙攣は、運動の後や高齢者では就寝中によくみられる症状です。筋ジストロフィーや筋萎縮性側索硬化症などの病気では、"こむら返り"を起こしやすいことがあります。
運動とは無関係に筋肉痛が起こる病気もあります。リウマチ性多発筋痛症は50歳以上の中高年者に多く、関節を包んでいる滑膜に炎症がおこる病気ですが、肩~上腕、臀部~大腿に筋肉痛を訴えます。
手や脚がふるえる・勝手に動く
これらの症状は不随意運動と呼ばれ、自分の意思とは関係なく、体が勝手に動いてしまう現象を意味します。体の一部だけ(手のふるえや、顔のピクツキ、足のむずむずする感じ等)の軽微なものから、全身に及ぶ重度なものまで含まれます。主な不随意運動の種類としては、ふるえ、舞踏運動、バリスム、アテトーゼ、ジストニア、ジスキネジア、ミオクローヌス、痙攣(スパズムとクランプ)などがあります。
ふるえ
人前で緊張のためふるえる場合や、寒いときに出現する場合は問題ありませんが、コップをもったり箸を使ったりするときに出現するふるえは病気の可能性があります。
ふるえの出現する状況に応じて大きく二つに分けられます。じっとしている静止時に出現するふるえと、姿勢時にふるえる場合があります。静止時に出現する代表的な疾患がパーキンソン病です。他のパーキンソン症候群でも同様に静止時に出現する場合がありますので、鑑別が必要です。
姿勢時のふるえは、水などの入ったコップで飲む時や、テレビを観ているときなどに出現することが多く、その場合は、本態性振戦である場合が少なくありません。
本態性振戦は、ふるえ以外の症状はありません。家族歴を認めることもあります。本態性振戦の症状がひどい場合は、治療が必要になります。また、内科的疾患でふるえが出現することもあります。特に甲状腺機能亢進症では、振幅の狭い、頻度の高いふるえが出現します。この他に、企図時や動作時に出現するふるえもあり、この場合は、小脳系の疾患の可能性があります。慢性アルコール中毒などでも動作時に出現することがあります。
ふるえの出現する部位は、頭、口、手足、いずれの場合もあります。声帯にふるえが出現する場合もあります。静止時、姿勢時、企図時そして動作時にふるえが認められる場合は、神経疾患の可能性がありますので、脳神経内科を受診する必要があります。
舞踏運動・アテトーゼ・ヘミバリズム
舞踏運動は、短くやや速い不規則な運動を言います。アテトーゼはゆっくりとした連続性のある動きで、舞踏運動と同時に出現することもあり、まるで踊っているような動きにみえます。ヘミバリズムは、大きく片側の上下肢を投げ出すような動きを言います。舞踏運動は、老人や妊婦にも観察されることがあります。
優性遺伝性舞踏病であるハンチントン病による舞踏運動が最も頻度的に高くなります。原因となる遺伝子は同定されておりますが、治療は難しく症状を抑える対症療法のみになります。
変性疾患は濃厚な家族歴を伴うことが少なくありません。第一近親者に同じ症状の患者さんがいる場合や、親になる可能性のある近親者にはカウセリングや遺伝子診断を勧めます。
ヘミバリズムは視床下核およびその周辺の脳梗塞が原因で発症します。通常は、6~8週で自然消失しますが、重度が高いケースは治療が必要となります。
ミオクローヌス
単一の筋または筋群に生じる短時間による筋収縮です。診断は臨床的に行いますが、電気生理学的検査により診断することがあります。健康な人でも眠りかけた時などに出現します。しかし、代謝疾患、肝不全、腎不全、心停止後の蘇生後などでも出現します。神経疾患では、アルツハイマー病、プリオン病であるクロイツフェルト-ヤコブ病で見られます。神経疾患か否かも含めてこのような症状がある場合は、原因を特定することが必要です。
ジスキネジア
抗精神病薬の長期投与で観察される遅発性ジスキネジアや、パーキンソン病のレボドパ長期治療での副作用としてのクネクネさせるような動きを言います。症状としては、「繰り返し唇をすぼめる、舌を左右に動かす、口をもぐもぐさせる、口を突き出す、歯を食いしばる、目を閉じるとなかなか開かない皺を寄せている、勝手に手が動いてしまう、足が動いてしまって歩きにくい、手に力が入って抜けない、足が突っ張って歩きにくい」などの訴えをします。薬で誘発されることが頻度的に高いので、抗精神病薬か抗パーキンソン病薬を服用していないか確認することが大事です。その上で急にご自身で薬を中止したりせず、医師に相談することが大事です。
ジストニア
長時間続く不随意な筋収縮を特徴として、異常な姿勢を強いられます。例えば体幹、上下肢、頸部がねじれたりします。原因は遺伝性のケースと脳の疾患、薬剤が原因で起こります。遺伝子の変異で発症する一次性と、疾患や薬剤で起こる二次性が存在します。ジストニアの起こる部位ですが、体の一部だけ(局所性ジストニア)、複数箇所に起こる場合(分節性ジストニア)、全身性に起こる場合(全身性ジストニア)があります。
ふるえや勝手に体の一部が動いてしまう症状は一過性に出現することもありますが、ここに説明した不随意運動が持続的に出現する場合は脳神経内科を受診することが大事です。
力が入らない
運動の指令は 脳 → 脊髄 → 末梢神経 → 筋肉 へと伝わり、実際に手足が動きます。
この経路のどこかに障害があると、脱力が生じることがあります。
手に力が入らない、足に力が入らないなどの症状があると上手に箸を使えなかったり、物を持っても落としてしまったり、歩きにくくなったりします。
特に体の片側の手足(例えば右の手足)が同時に動きにくくなったり、顔つきが変わったり、ろれつがまわらないときなどは、脳梗塞や脳出血などの緊急性の高い疾患の可能性があるので、なるべく早く受診されるようお勧めします。
また、脳だけでなく脊髄や手足の先にいく神経になんらかの障害があると、力が入らないことがあります。
力が入らない症状から考えられる疾患は
- 脳梗塞、脳出血
- 脳腫瘍
- 特発性正常圧水頭症
- 慢性硬膜下血腫
- 脊髄脊椎疾患
- パーキンソン病
- 多発性硬化症
- 脊髄小脳変性症、多系統萎縮症
- 筋萎縮性側索硬化症
などがあります。